みなさま、
家事、仕事、学校、
いつもお疲れ様でございます。
相変わらず、
暑い日が続いてますね!
水分補給、睡眠、休息
しっかり、とって
いつも頑張ってる
その体、労ってあげて下さい。
さあ、
HIPHOP好きの僕が、
惚れたKPOPについて
後半戦です!
今回も、初っ端から
トップスピードで
紹介していきますよ!
BTS(防弾少年団)
初期 2013〜2014
今や“世界のBTS”。
ビルボードを制し、
スタジアムを埋めるモンスターグループ。
正直、僕が一番グッとくるのは、
「防弾少年団」としてのBTS。
2013〜2014年、あの頃のバンタンです。
「No More Dream」
「Spine Breaker」
「War of Hormone」
初期の彼ら、普通に
ヒップホップアーティストだった。
サウンドもスタイルも、
Boom Bapど真ん中。
KPOPというよりも、
“韓国のストリートクルー”
という印象すらあった。
・太いビートに乗る、攻めたラップ
・テーマは“夢”“反抗”“自己証明”
完全にHIPHOPマインド。
MVでのスタイリングもガチでストリート。
キャップ、チェーン、ロングT、
迷彩、ジョーダン…
“あの時代のリアル”
を体現していたと思います。
影響されまくった僕の話(恥)
当時の僕、
完全に感化されていました。
・Off White
(学生には、高くて買えなかった)
・STUSSY
・ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB
この辺にどハマりして、
「我、ARMY。」みたいな顔して
ストリート歩いていました。(笑)
今思えば黒歴史。
でも、あれが青春です。
天才たちのサイファー:
RM / SUGA / J-HOPE
この3人、やばい。
スキル・声質・書くリリックの深み、
全部違うのに、
合わさると、とんでもない化学反応になる。
つまり“サイファー最強”。
当時、JUNG KOOKも
ラップパートに参加してて、
「こいつなんでも出来すぎだろ…」
って、なってました。
ダンス、ラップ、ビジュアル、
メインボーカル、絵も上手くて…。
すべて揃ってるからこそ、“黄金マンネ”
と呼ばれるのも、納得でした。
「MIC Drop」
世界に響いたHIPHOP魂。
Steve Aokiとのコラボバージョンは、
KPOP×HIPHOP×EDMの完璧な融合。
攻めたトラック、シニカルなリリック、
BTSの“あの頃の”反抗心が、
世界に突き刺さった瞬間。
余談ですが、
この曲で、世間に“バケハ”流行らせたの、
彼らだと思っております。(笑)
街の男たち、
みんな“バンタン風味”になっていた。
Agust D(SUGA)
“反骨のラッパー”
「KPOPアイドルのラッパー」
そんな言葉を
真っ正面から、ぶっ壊しにきた男がSUGA。
Agust D名義で放った一撃。
あれはもう、
“音楽”というより“魂の叫び”でした。
「Agust D」
速すぎるラップ、噛みつくような言葉。
韓国のリスナーからは
「韓流版Eminem」なんて
例えられたりもしてました。
SUGAはもともと、
「事務所にHIPHOP集団作るよ」って
話で入所したみたいですね。
(アイドルグループになるなんて
思ってなかった説もある)
だからこそ、
「アイドルって呼びたいなら勝手にしろ」
ってリリックが、重くて、
ぶっ刺さる。
アイドルとしての顔と、
アンダーグラウンドにいた頃の自分。
その葛藤の中で生まれた曲だからこそ、
あれほどの熱量と痛みがある。
まさに、ラッパーの“自我の爆発”。
BTSは進化した
でも、彼らは、
最初からHIPHOPでした。
だからこそ、
今のダンスミュージックスタイルも
ちゃんと“根っこ”があると思います。
そしてAgust Dは、
「KPOPに、本物のラッパーはいる」
ということを、
世界に知らしめた一人。
彼らの再始動。
“楽しみで仕方がない”ですね。
Red Velvet
スウィート × 毒の二面性
Red Velvet。
その名の通り、
甘さ(Red)と、深み(Velvet)。
鬼塚先生(GTO)
もビビるほどのpoison
言いたいことも、言えない世の中じゃ。
“poison“。
両極を行き来するコンセプトを、
ここまで完璧に体現できるグループが、
他にいるだろうか?
「Ice Cream Cake」
甘いだけじゃない、
不穏なアイスクリーム。
タイトルだけ見ると、
「え、ただの甘くて可愛い曲でしょ?」
って思いますよね?
でも、イントロから
すでに空気が違う。
・どこか影のあるメロディ
・ふわっと浮かぶようなトラック
・ヒヤッとさせるハーモニー
“少女っぽさ”を前面に押し出しながら、
その奥でチラつく “毒”。
言うなれば、
「ポップの皮をかぶったサイコポップ」。
この二重構造こそが、
Red Velvetの真骨頂。
注目したいのが、大サビ前。
アイリーンとジョイが魅せる、
ラップシーン。
それまでのキュートな
流れをぶった切るように、
テンポ感をグッと上げて、
高速で畳みかけてくる。
アイドルらしい可愛さの中に、
“スキル”と“緊張感”を忍ばせる巧みさ。
耳心地はいいのに、
心のどこかがザワッとする──
Red Velvetは、このバランスを熟知してる。
「Peek-A-Boo」
狂気を、遊びに変える。
イントロが鳴った瞬間から、
もう“不穏”。
・ピンと張ったような緊張感のあるリズム。
・ミステリアスに跳ねるシンセ。
・じわじわと迫ってくるようなベース。
なのに──
メロディはポップで、
サビは楽しげにすら聴こえる。
この“ギャップ”が、
めちゃくちゃ怖い。
MVでは、
ピザ配達員を誘い、
狩る“魔性の少女たち”。
衣装はカラフルなのに、
その瞳には一切の迷いがない。
明るさと不穏さが同居する。
“サイコスリラー系KPOP”
というジャンル。
Red Velvetが、それを築き上げた
のだと思います。
“ギャップ”で世界観を作る
Red Velvetは、「カワイイ」
だけじゃ終わらない。
むしろ、“不穏さ”や“毒”があるからこそ、
そのスウィートさにリアリティが宿る。
そのバランス感覚が、
他のガールズグループとはまるで違う。
音楽性も、ビジュアルも、スタイルも。
“Red Velvetのすごさ”。
・普通に踊ってるのにどこか演劇的
・笑顔なのに、目が冷たい瞬間がある
・衣装がポップでも、なぜか影を感じる
“見せ方のレベル”が一段上
なんだと思います。
「Ice Cream Cake」で、
甘さに忍ばせた毒を感じさせ──
「Peek-A-Boo」で、
その毒が完全に表へと現れる。
Red Velvetの魅力は、
この“振れ幅”にこそある。
・サイコポップ
・スウィートファンタジー
・毒を撒く少女たち
全部が合わさって、
“Red Velvet” なんだと思います。
NCT127
彼らはKPOPの中でも、
“尖りすぎた最前線”。
音もファッションもステージも、
全てが攻めの美学です。
”ただのアイドルじゃない感”
が、第一印象でバチバチ伝わりますよね。
「Cherry Bomb」
“美学は破壊の中にある”
「I’m the biggest hit〜」から始まる衝撃。
・ビートはシンプル、でも重い。
・ラップが曲の“武器”になっている。
・マークの低音ボイスが、
トラックに完璧にフィットしている。
あの声の入り方。
「音楽」じゃなくて「現象」レベル。
ステージングも含めて、
視覚・聴覚の攻撃系アートなんです。
「Kick It」
壁を壊して出てくるラップ
「New Thang!!」って咆哮で、
空気が一瞬で、変わる。
・曲全体が“戦うための音楽”
・テーマは“自分を解放する”、
この、精神HIPHOPど真ん中
にあたりますよね。
・マークのバース、攻撃的なのに流麗
・ダンス×ラップの瞬間、観客が沈黙
→爆発までの流れが美しい
ストリートと東洋美学の融合。
それをラップで成立させられるのは、
彼らだけ。
MARKという存在
ラップを“音”じゃなく、“武器”にした男
テクニック もちろんやばいです。
でもそれ以上に、
“彼の声そのものに感情が宿っています。”
高速ラップも、バウンスも、
メロディーラップも全部こなす。
でも、何より刺さるのは「声圧」。
マークのバースって、観客の意識、
かっさらう力がある。
「ラップ上手いアイドル」じゃない。
「音で支配する、音楽家」──それがMARK。
NCT127は、“曲もやばい”。
でもその中心に、
マークの声があるから。
ステージが
“爆発物”になるのだと思います。
MAMAMOO
“かっこよさ”で
正面から殴ってくる女たち。
“へえー、面白え女。”
最初はそんな印象でした。(笑)
でも、見れば見るほどわかる。
彼女ら、本物。
MAMAMOOってグループ、
初めて見た時、
「あ、プロ集団来た。」
全員、歌える。
全員、踊れる。
全員、キャラ立ってる。
なによりも
“自分を持ってる”感がハンパない
と、思いました。
KPOPガールズグループって、
どこか“揃ってる美しさ”を
求められがち。
MAMAMOOは、真逆。
「揃わなくても、
1人1人がHIPなんで。」
という感じで、
堂々とステージ立っている姿に
シビれました。
「HIP」
誰よりも己が、
1番カッコよくあれ。
そう言っているような感じ。
この曲、タイトルからして
“ぶちかましてる”。
ただのオシャレじゃない。
「HIP」=自分がかっこいいと信じること。
ビートはバウンシーで、グルーヴィー。
だけど、歌詞はゴリゴリ自己主張。
・SNSで何言われても気にしない
・他人の視線より、自分の美学
・“着たい服を着てる、それがHIP”
生き様そのものがHIP。
これ、完全にHIPHOP的な
メンタリティですよね。
パフォーマンスの説得力
・ソラのパワフルなハイトーン
・ファサの毒気と色気をまとった歌声
・ムンビョルのラップのキレ
・フィインのソウルフルな抜け感
全員が“主役”で“異端”で“圧倒的”。
ステージってより、“戦場”に立ってる感じ。
パフォーマンスで勝ち取りにきている。
HIP=自己証明
この曲は
こう言ってるんだと思います。
「他人がどう思うかなんて、関係ない。
自分が自分を誇れれば、それが一番HIP。」
これは、
ストリート出身のHIPHOPが
ずっと言ってきたこと。
どこかで繋がっている。
MAMAMOOは、
“型”にハマってない。
「こうあるべき」って価値観を、
ステージでぶっ壊してくる。
「HIP」って曲は、
自分を好きでいられる強さを
音楽でぶん殴って教えてくれる名曲。
BLACKPINK
“ガールズクラッシュ”なんて
もう通り越した。
これは、HIPHOPを纏った
最強の女たちの物語。
それぞれがソロでも世界で戦い、
結果を残し、存在感を証明してきました。
今や、“BLACKPINKの完全体”とは
4人それぞれの“個”が極まった集団。
つまり、
完成されたソロたちが合体した、
最終形態。
ドラゴンボールで、いえば
最強のラスボス。
純粋”悪”。魔人ブウ状態。
ブウも、ピンクだしな…(笑)
KPOPの枠を突き破り、
ストリートマインドと
グローバル感覚を武器に、
“次の時代”をぶち上げている。
「DDU-DU DDU-DU」
無敵の4人、世界に撃ち込んだ一弾。
イントロの銃声SEで
もう勝負ありました。
リサ&ジェニのラップライン。
完全に攻撃型
“I’m a boss bitch”の説得力が異常。
トラックは、
Trap〜Boom Bapのミックス。
サビのフックは”撃つ”のではなく、
“突き刺し”ている。
この曲で彼女たちはこう言ってる:
“女の子?誰の下につくって?”
BLACKPINKは
「可愛く強い」のではない。
強くて強い。
ただし、そこに“美しさ”
があるのが最大のギャップ。
「Kill This Love」
愛も、自分を殺すなら、撃ち殺す。
・愛に溺れない。
・泣いても立ち上がる。
・重厚なブラス×Trapビートで、まるで戦場。
ラップパートの
“言葉の刃”がえぐいです。
「Kill this love before it kills you」
=HIPHOP的“サバイブの哲学”。
ファッションも演出も軍隊ばり。
自分の感情すら支配する女たち。
これはもうKPOPじゃない。
“ストリートに生きる女の詩”
BLACKPINKはそれを、
音で、魅せました。
BLACKPINKが証明したもの
BLACKPINKは、
“アイドル”という枠を超えた存在。
彼女たちが鳴らす音は、
ただのKPOPじゃない。
HIPHOPの精神、
ストリートの美学、
グローバルの野心。
すべてを併せ持つ、時代の象徴。
ラップ、ダンス、ビジュアル、そして言葉。
どれを取っても“本物”。
BLACKPINKが世界で支持されるのは、
ただ人気だからじゃない。
「自分を信じて、自分で在る」
その姿が、音楽にちゃんと出てるから。
それこそが、HIPHOP。
そして彼女たちは、
そのマインドを、
最高に美しく鳴らせる最強のチーム。
最後に。
前編、後編合わせて
ここまで長い文章
見ていただきありがとうございました。
ここまで語ってきたのは、
彼ら、彼女らの
“アイドルっぽくない瞬間”です。
でも、“アイドル”
であることを忘れないプロ集団。
“みんなに愛されるキャラクターと美しさ”
“己を貫き通す強さ”
共存する瞬間なんです。
それって、
HIPHOPにおける”自分であること”
どこか重なると、思うんです。
KPOPは今、
ただのジャンルじゃない。
音楽的スキルも、
ファッションも、
言葉も、カルチャーも──
すべてを背負ってアップデートされている。
この進化を、
ただ“ブーム”として流すのは、
“もったいない。”
僕の大好きな
HIPHOPと、KPOPの共通点を見い出し
魅力を語ってきました。
しかし、どのジャンルにも、
どのカルチャーにも、
こういった重なる瞬間って
あると思うんです。
自分なりの視点で楽しむのもまた、
カルチャーの醍醐味だと思います。
“ただのアイドル”じゃ終わらない彼らを、
これからも追いかけていきたいです。
こういったカルチャーから、
刺激を受け、
あなた自身の心に宿る
“己を愛する美しさ”
“スタイルを貫き通すカッコよさ”
に気づいてもらえたら、
僕は幸せです。
なにかと、大変な毎日。
辛いこと、悩めること
あるかと思います。
迷っている時、
目標はなんだったのか。
分からなくなり
“自分を見失っている”
そんなにときに、
力になってくれる。
寄り添ってくれる。
そんなカルチャーが、
僕は、大好きです。
音楽がある限り、
僕たちはまた出会える。
だから、
次回も楽しみにしててくださいね。
またここで
会いましょう。
ではまたっ。
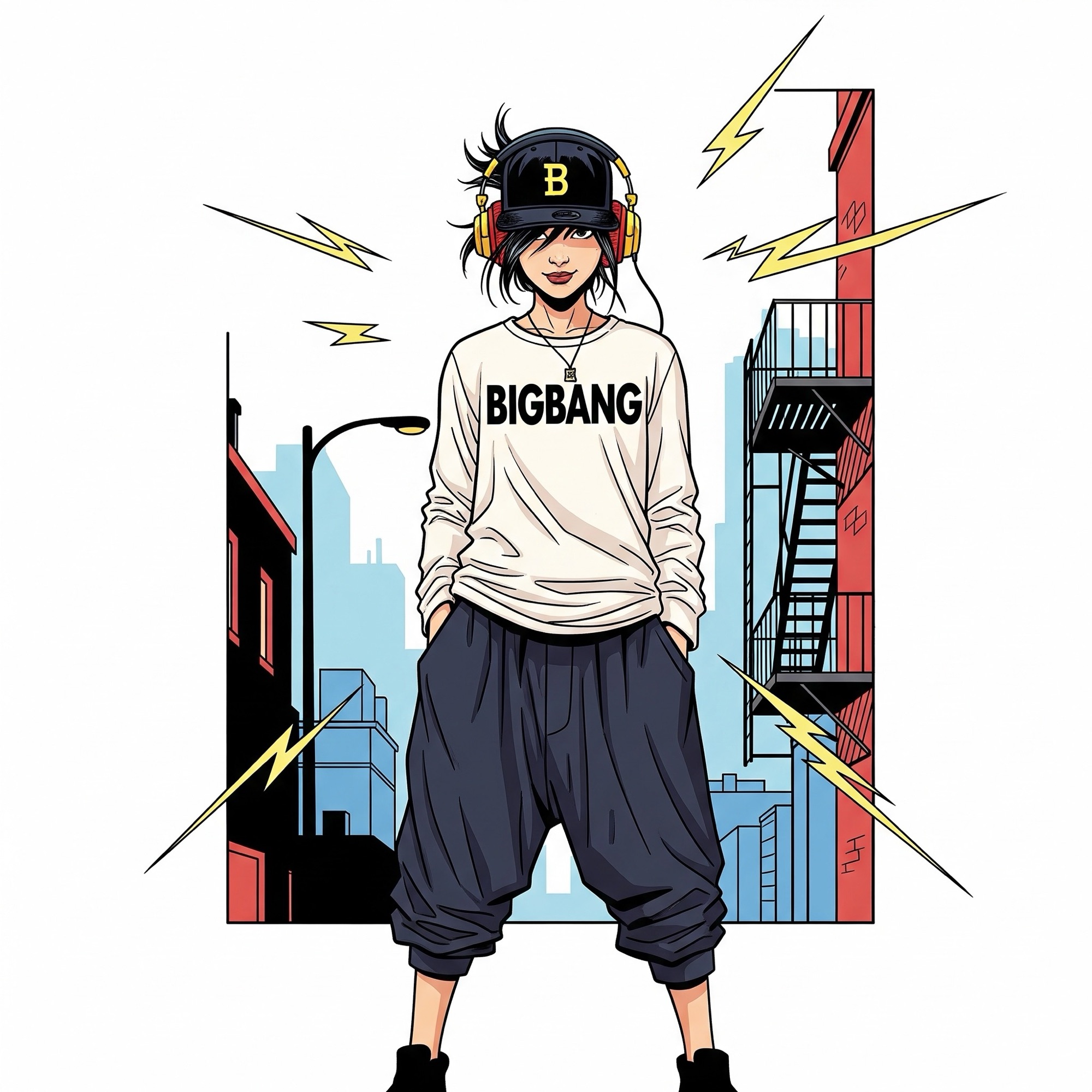


コメント