最後に、絵本を読んだのは、
いつですか?
もしかしたら、
ご家庭や、身内で、
お子さんがいる人は、
直近で、読んだことあるかもしれません。
では、
1人で、絵本を
熟読したのはいつですか?
そう聞くと、かなりの
人数減ると思うんです。
「絵本って…。 」 と、
思う方もいるかもしれません。
侮るなかれ。
絵本って、考えたら
めちゃくちゃすごいと思うんです。
数少ない文字数。
漢字も使わずに。
少ないページ数で。
制限された環境なか、
魅せてくれる感じ。
めちゃくちゃ、
クリエイティブじゃね?
そんなわけで。
絵本で、
あなたが特に、
好きだった作品はなんですか?
あの頃の。
純粋無垢だった頃の、
好きだった作品を辿れば、
あなたの深層心理が、
読み取れるかもしれません。
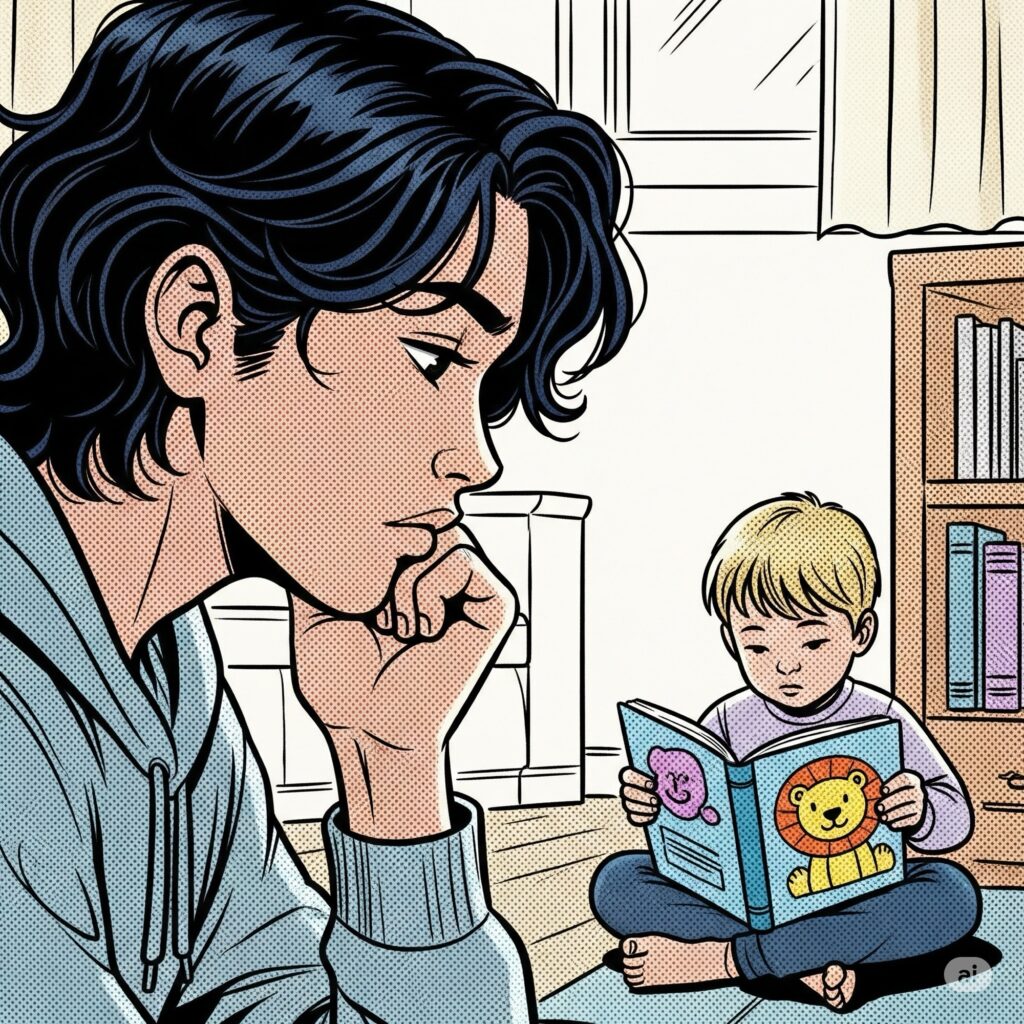
自分って、
こう思っていたのか!と。
幾つか、作品を取り上げていきます。
皆さんも好きだった作品を
思い返しながら、
読んでいただけると、幸いです。
今後、本屋さんへ行き、
絵本ゾーン通りかかるあの瞬間。
少し見え方が
変わるかもしれません。
私の推し本
まずは、僕の当時好きだった
絵本を紹介させて頂きます。
「ネズミくんのチョッキ」
幼稚園に置いてあって、
お気に入りでした。
表紙のデザインがシンプルで、
ミニマルな感じが
視覚的もよくて、なんか好きでした。
内容 :
ネズミくんのお母さんが、
チョッキを編んでくれた。
ネズミくんはそれを自慢気に着ていたけど、
友だちの動物たちが次々に
「ちょっと着てみてもいい?」と頼んでくる。
ライオン、ゾウ…と、
どんどん大きな動物たちが登場して、
そのたびにチョッキが
ビリビリに伸びていく…。
最終的に、ネズミくんのチョッキは
着れない形になって、
ネズミくんは涙目。
最後のオチで、
ちょっと笑えるシュールさがある。
ハートフルな終わり方。
読み取れる心理:
・「優しさ」と「断れなさ」
・自分の大事なものを人に譲りすぎる葛藤
・見た目の違い、力の差、社会的立場の象徴
・「気づいたら、自分の居場所が
なくなってた」感覚
→ “他者に譲る”ことと、“自分を守る”ことの
バランスって、子どもの頃から
無意識に意識していたのかも。
→ 誰かと共有することに喜びを
感じてた人は、「共感」や「共存」が
生きる軸になっている可能性ある。
「てぶくろ」(ウクライナ民話)
全体的に、温かみのある雰囲気で
癒される。優しい気持ちに
なれる気がして好きでした。
内容 :
おじいさんが落とした手袋を、
森の動物たちが次々に「入れて」
といい、入っていく。
ねずみ、かえる、うさぎ、きつね、
いのしし、くま…
とにかくどんどん増えて、
手袋はぱんぱんになる。
最終的に、「これ以上は無理だろ!」
という、サイズになり、
ちょっとしたきっかけで、
動物たちはびっくりし、飛び出していく。
読み取れる心理 :
・「みんなと一緒にいたい」という欲求
・狭い空間=安心・帰属意識の象徴
・境界のあいまいさ
(どこまで受け入れていいのか)
・「共有の快」と「パンクする不安」の同居
→ “居場所”や“仲間との一体感”
を求める気持ちがベース。
→ 限られた空間に、どこまで他人を
受け入れられるか?という
無意識の問いでもある。
両作品に、共通しているテーマは、
“共有”、”共存”
と、いう感じ。
幼稚園の頃は、
すごく泣き虫でした。
人前話すのは、苦手だったし、
何人かでグループ作り、
何かをするイベント。
嫌で仕方なかった。
何かあるたびに、
すぐに泣いていた。
人と関わるのがすごく苦手。
だからこそ、
共有、共存 のあり方を
知らずして、求めていた
のかもしれないです。
どうですか?
こんな感じで見ていくと、
なんとなく、その人の”深層心理”
読み取れそうな気がしませんか?
次に、代表的な作品を挙げて、
そこから読み取れる
“深層心理”について、迫っていきます。
当時、あなたが好きだった作品が
あるかもしれません。
名作から読み取る深層心理
ここからは、名作たちの内容に触れ、
そこから、”読み取れる深層心理”について
紹介していきます。
「三匹の子ぶた」
内容:
3匹の子ぶたが、それぞれ
藁・木・レンガの家を建てる。
そこから、オオカミが襲ってくるが、
藁・木の家は潰されてしまう。
レンガの家だけが耐える。
努力と準備の重要性を描く寓話。
⸻
読み取れる心理:
・安全を求める本能(=レンガの家)
・手抜きへの不安、未来への備えの重要性
・失敗と成功、因果関係に対する理解
→ 「どの子ぶたが好きだったか」
によって、”物事に対する見え方”、
“取り組み方のクセ”が出ると思います。
このお話では、レンガの家(堅実派)
が正解でした。
しかし、環境や、タイミング、内容
によって、答えが変わるかも。
→ レンガ派=現実的で慎重
藁・木派=自由や即興性を重視
→ 子どもの頃の“家=居場所”に対する
考え方が反映されているのかもしれません。
「はらぺこあおむし」
内容 :
お腹を空かせたあおむしが、
毎日いろんな食べ物を食べていく。
どんどん大きくなって、
やがてさなぎになり、美しい蝶に変身する。
⸻
読み取れる心理 :
・成長と変化への好奇心・不安
・「自分が何に変わっていくのか」への関心
→ 成長し、「変わること」への
ポジティブな感情を持っているのか、
それとも、「変化に対する不安」
を内に秘めていたか。
→ 自己肯定感、発達、進化など。
“人生のプロセス”に敏感な人
なのかもしれませんね。
・本のカラクリが面白い
→アート的な感覚を幼少期から、
持ち合わせていたのかもしれません。
「ぐりとぐら」
内容 :
野ねずみの「ぐり」と「ぐら」が
森で大きなたまごを見つける。
大きなフライパンでカステラを焼き、
森の仲間たちと仲良く、
みんなで一緒に食べる。
⸻
読み取れる心理 :
・仲間と喜びを共有したい欲求
・創造することの楽しさ(=料理)
・自然の中で暮らす理想像
→ 「自分の手で作ったものを、
誰かと分かち合う幸せ」
に惹かれていたのかも。
→ 「孤独よりも共生」 「競争よりも共創」
を大事にしている人。
「三びきのやぎのがらがらどん」
内容 :
3匹のやぎが橋を渡って草を
食べに行こうとするが、
橋の下にトロルがいる。
小さなヤギから順番に渡り、
賢くトロルをかわしていく。
最後に一番大きなヤギが
トロルを吹き飛ばし、全員無事渡れる。
⸻
読み取れる心理 :
・知恵で危機を乗り越える知性的な価値観
・「順番を守る」「機転で対処する」ことの美学
・不条理な強者(=トロル)への反撃願望
→ トロル=“社会の理不尽”や
“怖い大人”の象徴。
→ 「頭を使えば自分より、
大きな問題も超えられる」
と、いう、逆転思考や希望を
大事にしてる傾向あるのかも。
→ 下剋上、知恵勝ちへの
あこがれを内に秘めたタイプかも。
まとめ
どうでしたか?
好きな作品は、ありましたか?
「あ、確かにそうかも」
って、思うような
ところはありましたか?
自分の深層心理って、
なかなか読み取れないもの。
その人の本棚(持ち物でもいい)や、
買い物かごに
入っている本(もの)を見れば、
・その人が惹かれるもの
・その人の価値観
わかるような気がします。
写し鏡みたいなものですよね。
さらに、それが
幼少期に、心惹かれていたもの。
絵本という、
「シンプルかつ、内容が凝縮している」もの。
そこから、自身の”深層心理”を
読み取るのって、面白いと思うんです。
もし、身近に、
お子さんがいる方は
なぜ、この子は
この絵本が好きなんだろう?
意識して見てみると
その子の理解が
より深まるかもしれませんね。
ぐりとぐらが作っていた
“カステラ”
あれ、
美味しそうだったよなあ。
当時、
食べたくて仕方なかった。
今見ると、
菌とか、やばいし、
腹下しそうだよな。
(ネズミが作ってるし。。)
…。
“嫌な大人” に、
なってしまった。
ではまたっ。(笑)
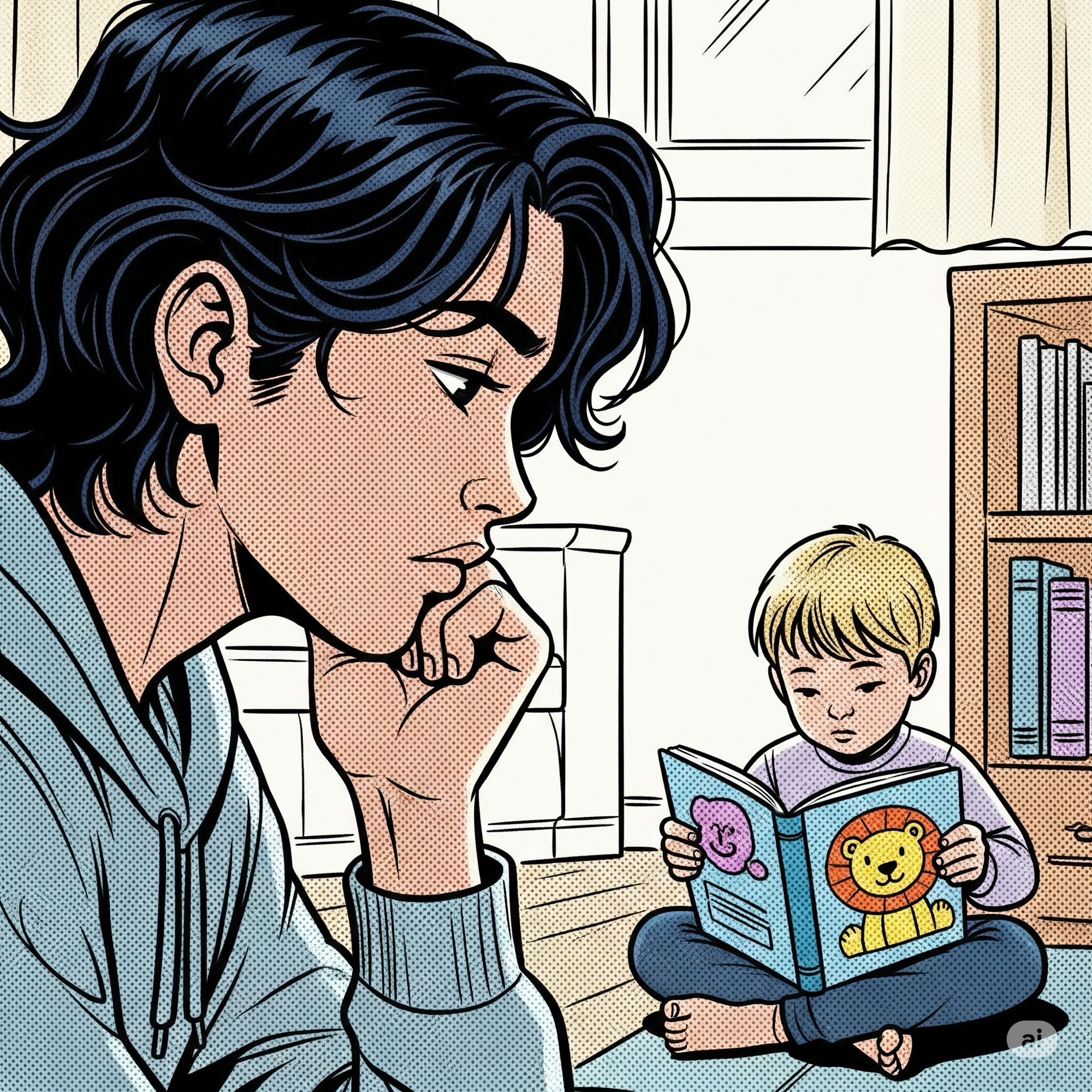


コメント